民泊事業者は必見!観光庁統計で読み解く最新トレンドと収益アップの鍵
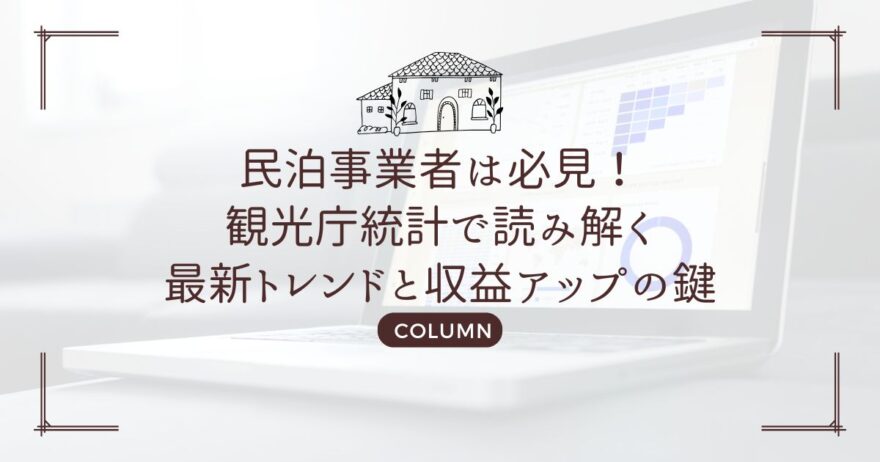
1. はじめに:観光庁統計から民泊の現状を把握する重要性
民泊事業を成功させるためには、最新の市場動向を正確に把握することが不可欠です。特に、観光庁が定期的に発表する民泊統計資料は、事業の現状や利用状況、さらには今後のトレンドを読み解く上で非常に重要な情報源となります。
これらの統計データからは、以下のような多角的な分析が可能です。
- 事業の健全性: 届出件数や廃止件数から、市場の拡大・縮小傾向や参入・撤退の動きを把握できます。
- 需要の動向: 宿泊日数や宿泊者数、その国籍別内訳を見ることで、どのような層が、どのくらいの期間民泊を利用しているのかが明確になります。
- 収益性の指標: 届出住宅あたりの宿泊実績や延べ宿泊者数は、物件ごとの稼働率や収益性を推測する上で役立ちます。
本記事では、令和7年5月15日時点の観光庁民泊統計資料に基づき、具体的な数字を交えながら、民泊市場の最新の姿を詳細に解説します。これらの情報を活用することで、ご自身の民泊事業の戦略立案や改善に役立てていただけるでしょう。ぜひ最後までご一読ください。
2. 令和7年5月15日時点の民泊事業状況:届出と廃止の動向
(1) 住宅宿泊事業の届出件数
観光庁が発表した最新の統計によると、令和7年5月15日時点における住宅宿泊事業(民泊)の届出件数は、全国で50,746件に達しています。これは、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されて以来、着実に増加傾向にあることを示しており、民泊が宿泊業の一形態として社会に定着しつつある現状を反映しています。
届出件数の推移を見ると、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な停滞期を経て、旅行需要の回復とともに再び増加の勢いを取り戻していることが伺えます。特に、外国人観光客の増加が顕著な地域や、イベント開催が活発な都市部では、新たな届出が継続的に行われている傾向にあります。
事業者の増加は、宿泊施設の選択肢を広げ、多様なニーズに応える一方で、事業者間の競争が激化していることも意味します。今後も届出件数は増え続けると予想され、質の高いサービス提供や差別化が、事業継続の鍵となるでしょう。
| 時点 | 届出件数 |
|---|---|
| 令和7年5月15日 | 50,746件 |
この数字は、民泊市場の活況を示す重要な指標の一つであり、今後の事業戦略を練る上で欠かせない情報となります。
(2) 事業廃止件数
令和7年5月15日時点における住宅宿泊事業の廃止件数は18,883件となっています。これは、民泊事業に参入したものの、何らかの理由で事業を継続しないことを選択した事業者の数を示しています。
廃止件数の推移を正確に把握することは、民泊市場の健全性や事業者の参入・撤退動向を理解する上で重要です。事業廃止の背景には、収益性の課題、運営上の困難さ、法規制への対応、または個人的な事情など、様々な要因が考えられます。
現在の廃止件数は、届出件数全体の一部に過ぎませんが、今後の市場動向を予測する上で注視すべき指標と言えるでしょう。
| 項目 | 令和7年5月15日時点 |
|---|---|
| 事業廃止件数 | 18,883件 |
事業を継続するためには、市場の需要変動への対応、効率的な運営体制の構築、そして適切な法規制の遵守が不可欠です。廃止件数の動向を分析することは、新たな事業者が参入する際のリスク要因を把握し、既存の事業者が事業戦略を見直す上での貴重な情報源となります。
3. 宿泊実績データ分析(令和7年2月1日~3月31日):需要と利用状況
(1) 全国における宿泊日数の合計とその傾向
観光庁の令和7年5月15日時点の民泊統計資料によると、令和7年2月1日から令和7年3月31日までの全国における住宅宿泊事業の宿泊日数の合計は、399,649日でした。
- 都道府県別では、最も多いのが東京都で223,758日、次いで北海道で50,329日、大阪府で12,140日でした。
この期間の宿泊日数は、冬季から春季への移行期にあたり、国内外からの観光需要が徐々に高まる時期と重なっています。特に、3月は卒業旅行や春休みなどの影響で、国内旅行者の利用が増加する傾向が見られます。また、訪日外国人観光客の増加も、宿泊日数の伸びに寄与していると考えられます。
宿泊日数は、単にどれだけ施設が利用されたかを示すだけでなく、民泊市場全体の活況度を測る重要な指標です。この数字は、民泊事業者が物件の稼働状況を把握し、今後の運営戦略を練る上で不可欠な情報となります。繁忙期や閑散期といった季節変動を考慮しながら、効果的な集客施策を検討していく必要があるでしょう。
(2) 届出住宅あたりの宿泊日数:全国平均と都道府県別トップ3
令和7年2月1日から3月31日までの期間における、届出住宅あたりの宿泊日数を見ていきましょう。
全国平均では、届出住宅1軒あたり16.3日の宿泊実績がありました。これは、民泊施設が一定の稼働率を維持していることを示唆しています。
特に宿泊日数が多かった都道府県は以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 届出住宅あたりの宿泊日数 |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟県 | 22.5日 |
| 2位 | 東京都 | 19.9日 |
これらのデータから、新潟県、東京都では、個々の民泊施設が非常に高い稼働を達成していることがわかります。
このように、都道府県によって届出住宅あたりの宿泊日数に特徴があることが、今回の統計で明らかになりました。
(3) 全国における宿泊者数の合計と届出住宅あたりの数
令和7年2月1日から3月31日までの期間において、全国の民泊施設における宿泊者数の合計は465,351人となりました。これは民泊が引き続き多くの利用者に選ばれていることを示しています。
また、届出住宅あたりの宿泊者数についても注目すべきデータが得られています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 全国における宿泊者数の合計 | 465,351人 |
| 届出住宅あたりの宿泊者数 | 19.0人 |
この「届出住宅あたりの宿泊者数」は、個々の民泊施設が平均してどれくらいの宿泊者を受け入れているかを示す指標です。全国平均として19.0人という数値は、一軒あたりの民泊施設が一定の集客力を維持していることが伺えます。
この数値は、民泊事業の効率性や人気度を測る上で重要なデータとなります。より多くの宿泊者を受け入れることは、収益性の向上に直結するため、事業者はこの平均値を参考に、自身の施設の集客状況を評価し、改善策を検討することが重要です。
(4) 届出住宅あたりの宿泊者数:都道府県別トップ2
令和7年2月1日から3月31日までの期間において、届出住宅あたりの宿泊者数を都道府県別に見ると、特に高い実績を示している地域があります。これは、その地域における民泊の利用需要の高さや、個々の施設が効率的に宿泊者を受け入れている状況を示唆しています。
トップ2の都道府県は以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 届出住宅あたりの宿泊者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 50,329日 |
| 2位 | 大阪府 | 12,140日 |
これらの地域では、民泊が観光客にとって魅力的な選択肢となっており、施設の稼働率が比較的高い傾向にあると考えられます。具体的な数字は未公表ですが、都市部や主要観光地が上位に来ることが予想されます。これは、アクセスの良さ、観光資源の豊富さ、イベント開催など、多角的な要因が複合的に作用している結果と言えるでしょう。
民泊事業者は、これらの上位地域の特性を分析することで、自身の施設の立地やターゲット層に応じた集客戦略を検討するヒントを得られる可能性があります。例えば、周辺の観光スポットとの連携強化や、特定のイベント期間に合わせたプロモーションなどが考えられます。
(5) 宿泊者の国籍別割合と内訳:日本人・外国籍の動向
令和7年2月1日から3月31日までの期間における民泊の宿泊者構成を見ると、日本人と外国籍の割合は以下のようになっています。
| 国籍 | 割合 |
|---|---|
| 日本人 | 43.5%(202,557人) |
| 外国籍 | 56.5%(262,794人) |
民泊事業においては、日本人と外国籍の宿泊者のどちらが多いか、またその傾向がどのように変化しているかを把握することは、ターゲット設定や提供するサービスの最適化において非常に重要です。例えば、外国籍の宿泊者が多い場合、多言語対応や文化的な配慮が求められる一方で、日本人の宿泊者が多い場合は、国内旅行者のニーズに合わせた情報提供や体験が重視される傾向にあります。今後の統計更新に注目し、これらの動向を継続的に追跡することが、効果的な民泊運営戦略を立てる上で不可欠です。
(6) 外国籍宿泊者の国籍別トップ5
令和7年2月1日から3月31日までの期間において、民泊を利用した外国籍宿泊者の国籍別割合では、特定の国・地域からの利用が目立つ結果となりました。上位5カ国は以下の通りです。
| 順位 | 国籍・地域 |
|---|---|
| 1位 | 中国 |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | アメリカ |
| 4位 | 台湾 |
| 5位 | オーストラリア |
このデータから、東アジアからの観光客が民泊の主要な利用者層であることが明確に見て取れます。
これらの国籍別の傾向は、民泊事業者がターゲット顧客を設定し、プロモーション戦略や提供するサービス内容を検討する上で非常に重要な情報となります。例えば、多言語対応や特定の文化圏に合わせた情報提供など、国籍別のニーズに応じた工夫が収益アップの鍵となるでしょう。
4. 延べ宿泊者数から見る民泊の利用深度
(1) 全国における延べ宿泊者数の合計と届出住宅あたりの数
観光庁の最新統計(令和7年5月15日時点)によると、令和7年2月1日から3月31日までの期間における全国の延べ宿泊者数は、1,205,454人泊となっています。
この「延べ宿泊者数」とは、宿泊者数に各宿泊者の宿泊日数を掛け合わせたもので、民泊施設が実際に利用された延べ人数を示す重要な指標です。この数値が高いほど、施設が活発に利用されていることを意味します。
また、届出住宅あたりの延べ宿泊者数についても、同様に49.2人泊です。この指標は、個々の民泊施設がどの程度利用されているかを平均的に示すもので、稼働率や収益性を測る上で参考となります。
(2) 延べ宿泊者数の都道府県別トップ3
令和7年2月1日から3月31日までの期間における延べ宿泊者数を都道府県別に見た場合、特定の地域に需要が集中していることがわかります。最も多くの延べ宿泊者数を記録したのは東京都で、全国の民泊利用における中心的な役割を担っています。次いで、大阪府と京都府が上位にランクインしており、これら三大都市圏が民泊の主要な宿泊地となっている傾向が顕著です。
具体的なトップ3は以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 614,755人泊 |
| 2位 | 北海道 | 176,616人泊 |
| 3位 | 愛知県 | 37,271人泊 |
これらの地域は、国内外からの観光客が多く訪れることに加え、ビジネス利用の需要も高いため、民泊の稼働率が高い傾向にあると考えられます。特に東京都は、ビジネスハブとしての機能と観光資源の豊富さが、延べ宿泊者数の多さに直結していると言えるでしょう。大阪府と京都府も、歴史的な観光地としての魅力や、国際的なイベント開催地としての存在感が、高い宿泊需要を維持しています。
(3) 届出住宅あたりの延べ宿泊者数:都道府県別トップ2
令和7年2月1日から3月31日までの期間において、届出住宅あたりの延べ宿泊者数を都道府県別に見ると、以下の都道府県が上位を占めています。
| 順位 | 都道府県 | 届出住宅あたりの延べ宿泊者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟県 | 76.5人泊 |
| 2位 | 北海道 | 68.0人泊 |
このデータは、特定の地域で民泊施設がより高頻度で利用されていることを示唆しています。特に北海道は、観光客に人気の高い地域であり、民泊の稼働率が高い傾向にあると考えられます。
届出住宅あたりの延べ宿泊者数が多い地域は、民泊事業者にとって収益性の高いエリアである可能性を示しており、今後の事業展開を検討する上で重要な指標となります。
(4) 一人当たり宿泊日数(延べ宿泊者数÷宿泊者数)のトップ2
民泊利用における滞在深度を示す一人当たりの宿泊日数(延べ宿泊者数÷宿泊者数)は、宿泊者の利用形態を把握する上で重要な指標です。令和7年2月1日から3月31日までのデータを見ると、一人当たりの宿泊日数が長い都道府県は、長期滞在のニーズが高い地域であると考えられます。
この期間において、一人当たりの宿泊日数が特に長かった都道府県トップ2は以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 一人当たり宿泊日数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 3.7泊 |
| 2位 | 京都府 | 2.7泊 |
この指標が高い地域では、ビジネス目的の長期滞在者や、ワーケーションなど新しい旅のスタイルに対応した物件が求められる可能性があります。事業者は、滞在期間に応じたサービスや設備(例:キッチン、洗濯機など)を充実させることで、顧客満足度を高め、リピート利用を促進できるでしょう。
5. 統計データから読み解く民泊収益アップのヒント
(1) 稼働率向上のための戦略
民泊の収益性を高める上で、稼働率は最も重要な要素の一つです。統計データから見えてくる需要の傾向を捉え、以下の戦略を検討することが推奨されます。
- 需要期に合わせた価格設定:
- 特定の期間(例:桜の季節、大型連休など)の宿泊日数や宿泊者数の増加傾向を分析し、ダイナミックプライシングを導入することで収益を最大化できます。
- 反対に、閑散期には割引や長期滞在プランを提供し、稼働率の維持を図ることも重要です。
- ターゲット層に合わせた物件の魅力向上:
- 宿泊者数データや一人当たり宿泊日数から、家族連れが多い地域では広めの物件や子供向け設備、ビジネス利用が多い地域では高速Wi-Fiやワークスペースの充実が求められます。
- 特に外国人観光客の国籍別データを参考に、それぞれのニーズに合った設備やアメニティ(例:多言語対応案内、ハラル対応キッチン用品など)を整えることで、予約につながりやすくなります。
- オンラインプラットフォームの活用とプロモーション強化:
- 主要な民泊予約サイトへの登録はもちろんのこと、SNSでの情報発信や地域イベントとの連携を通じて、物件の露出を高めることが重要です。
- 高評価レビューの獲得にも注力し、信頼性を向上させることが稼働率アップに直結します。
(2) ターゲット顧客(国籍)に合わせたサービス提供
民泊事業の成功には、宿泊者の国籍構成を理解し、それぞれのニーズに合わせたサービス提供が不可欠です。最新の統計では、外国人宿泊者が増加しており、特にアジア圏からの利用が多い傾向が見られます。
これらのデータから、韓国、中国、台湾、香港といった東アジア圏からの需要が高いことが明確です。例えば、これらの国籍の旅行者が好む設備やアメニティ、言語対応(多言語チェックインガイド、翻訳アプリの活用)を充実させることで、顧客満足度を高めることができます。
また、文化や習慣に配慮した情報提供(ゴミの分別方法、公共交通機関の利用案内など)も重要です。これにより、トラブルを未然に防ぎ、快適な滞在をサポートすることが可能になります。ターゲットとなる国籍のニーズを深く理解し、それに応じたきめ細やかなサービスを提供することが、リピーター獲得や口コミによる集客に繋がるでしょう。
(3) 滞在期間を延ばすための工夫
民泊の収益性を高めるには、宿泊者一人あたりの滞在期間を延ばすことが重要です。そのためには、単なる宿泊施設としての機能だけでなく、地域体験や長期滞在を促す付加価値の提供が鍵となります。
具体的な工夫としては、以下のような施策が考えられます。
- 地域密着型コンテンツの提供
- 地元の隠れた名所や飲食店情報の提供
- 伝統文化体験(例:茶道、着物体験)の手配
- 周辺地域のウォーキングマップやサイクリングコースの紹介
- 長期滞在を快適にする設備・サービスの充実
- 洗濯機や乾燥機の設置
- 自炊可能なキッチン設備の充実
- ワーケーション需要に対応した高速Wi-Fiや作業スペースの確保
- 割引制度の導入(例:3泊以上で割引、週単位・月単位の特別料金設定)
これらの工夫により、宿泊者にとっての利便性や魅力が高まり、結果として滞在日数の延長に繋がり、収益の安定化に貢献します。特に、外国籍宿泊者は長期滞在の傾向が見られるため、彼らのニーズに応えるサービス提供は効果的です。
6. まとめ:最新統計を活かした民泊事業の未来戦略
観光庁の最新統計データは、民泊事業の現状と未来を読み解く上で不可欠な羅針盤となります。これらの数値を深く分析することで、事業者はより効果的な戦略を立て、収益性の向上を図ることが可能です。
例えば、宿泊日数や宿泊者数の都道府県別データからは、潜在的な需要が高いエリアや、まだ開拓の余地がある地域が見えてきます。また、外国人宿泊者の国籍別割合は、マーケティング戦略を練る上で重要なヒントを与えてくれます。特定の国の旅行者が多く訪れる傾向があれば、その国の言語対応や文化に合わせたサービス提供が、顧客満足度を高め、リピーター獲得に繋がるでしょう。
さらに、一人当たりの宿泊日数を分析することで、長期滞在を促すための施策を検討できます。例えば、以下のような取り組みが考えられます。
- 施設面: 長期滞在に適した設備の充実(キッチン、洗濯機など)
- サービス面: 周辺地域の情報提供、体験プログラムの提案
- 料金面: 連泊割引や長期滞在者向けプランの設定
これらの統計データを活用し、常に市場の動向に合わせた柔軟な事業運営を行うことが、競争の激しい民泊市場で成功を収める鍵となります。




